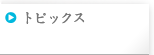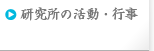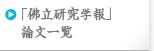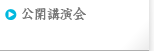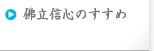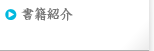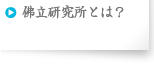-
- 2019
2016
2015
2014
2013
2012
122011
2010
2009
2008
2007
2006
2004
2003
1990
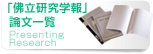
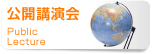
- 仏教のススメの過去の記事
- 2016年 3月
- 2016年 1月
- 2015年 12月
- 2015年 11月
- 2015年 10月
- 2015年 8月
- 2015年 7月
- 2015年 6月
- 2015年 5月
- 2015年 3月
- 2015年 2月
- 2014年 12月
- 2014年 11月
- 2014年 10月
- 2014年 8月
- 2014年 7月
- 2014年 5月
- 2014年 4月
- 2014年 3月
- 2014年 2月
- 2014年 1月
- 2013年 12月
- 2013年 9月
- 2013年 8月
- 2013年 7月
- 2013年 6月
- 2013年 5月
- 2013年 2月
- 2012年 12月
- 2012年 11月
- 2012年 8月
- 2012年 4月
- 2012年 3月
- 2012年 2月
- 2012年 1月
- 2011年 10月
- ⑧無智の信心を大切に ―智慧(ちえ)と知識(ちしき)―
- 2012年12月11日(火)
○「無智宗」(むちしゅう)の教えの意味とその大切さ
―人間の知識の危うさを知って―
前回まで三回にわたって「参詣の大事」のテーマで、「道場の能所(のうじょ)」や「親近(しんごん)と給仕(きゅうじ)」等について記しました。今月は当宗の信行における「無智の信心」の大切さについて申しあげます。特にお役中は「無智」の意味を誤解のないよう正しく理解していただき、それを踏まえて他のご信者を指導していただきたいのです。
さて、ご承知のように、人間のすぐれた点は、あらゆることを考える知能を持っていることです。そのおかげで万物の霊長として地球上のあらゆる生物に君臨し、高度な文化や文明を築き上げて繁栄してきました。特に科学技術の発達は目覚ましく、私たちはその大きな恩恵を受けています。
しかしその反面、環境は汚染・破壊され、核の脅威や資源の枯渇、地球の温暖化や貧富の格差の増大、社会・経済の不安、戦争・テロ・犯罪等に脅(おび)えているのも厳然たるお互いの姿であり、しかも依然として明日の自分の運命さえ知ることができないのです。人智の危うさ、頼りなさをよく知らねばなりません。
よく考えてみれば、凡夫の智恵・知識は、基本的に自己本位であり、貪欲(とんよく・我欲)を根として働いているものです。そしてそうである限り、働かせれば働かせるほど争いが激化し、ついには互いを不幸や破滅に導くものなのです。み仏はそうした浅ましい人間の姿を「不択禽獣(ふじゃくきんじゅう)」(禽獣(きんじゅう)を択(えら)ばじ・譬喩品)と示されています。餌(え)を争い、共食いすら辞さない猛獣や猛禽の類(たぐい)と何ら異ならない、いや高度な技術を持つだけなお危ういと仰せなのです。こんなお互いが真実の幸福に向かう方法は、貪欲を根とする凡夫の智恵の働きをとどめ、素直正直な心になってみ仏の大きな智慧をそのまま無条件でいただくほかないのです。
開導聖人が御教歌に
末法は智慧をとゞめて信をとり となへて妙の門に入るなり
(てこのかたま 扇全十五巻一三七頁)
とお示しなのは、まさしくこのことをお諭しくださるのです。
門祖日隆聖人は、当宗の特色を十二の宗名(しゅうみょう)としてお示しくださった(いわゆる「十二宗名」)のですが、その中で「無智宗」「信心宗」と仰せになられたのは、まさしくここのところを指しておられるのです。
つまり無智宗の「無智」とは、貪欲を本(もと)とする凡智(私[わたくし]・我[が])の働きをとどめよ、ということです。しかも仏智・仏慧(ぶって)は凡智で理解しようとして理解できるものではなく、ただ信ずることによってのみいただけるものですから、信心こそが唯一のいただく秘訣(ひけつ・信心宗)なのです。仏弟子中で智慧第一といわれた舎利弗尊者(しゃりほつそんじゃ)ですら、自分の智慧を捨て、信心をとることによってはじめて成仏を果たされます。法華経譬喩品(ひゆほん)で「汝(なんじ)、舎利弗すら、尚(なお)この経においては、信を以(もっ)て入ることを得たり。(乃至)己(おの)が智分(ちぶん)にあらず。(汝舎利弗 尚於此経 以信得入[いしんとくにゅう]〈乃至〉非己智分[ひこちぶん]」と示された通りです。
ましてやお互いは尊者にも遠く及ばない末法の凡夫です。日蓮聖人はこの大事を「慧又堪(えまたた)えざれば信を以て慧に代(か)へ信の一字を詮(せん)と為す」(四信五品抄[ししんごほんしょう])と仰せです。戒律を守る等の六度行(ろくどぎょう・六波羅蜜[ろくはらみつ]を行ずる修行)など全く手にあわない凡夫にとって、み仏のお悟りのすべてがこめられた御題目を受持信唱するだけの一行で、み仏の智慧のすべてがそのまま私共に頂戴できるというのは、最後に遺(のこ)された誠に有難い大慈悲の極(きわ)みではありませんか。
習い事でも、上達の秘訣は、できれば最初から優(すぐ)れた先生について指導を受け、教え通りにそのまま身に付けていくことです。もし先に自己流の悪いくせが付いていれば、まずそのくせを取り除きながら、正しい技法や心得を修得してゆかねばなりません。我流を捨て切れなかったり、誤った教え(それは、いわゆる“世間の常識”であることもある)に左右されていては、真の上達はおぼつかないわけです。素直さと、信じて貫いていく心こそが上達と成長の基本であり、生きたものごとのまん中にすっと入っていく心なのです。
○智慧と知識―いのちの世界に入るには智慧・霊性―
「無智が大事」というのは「何も学習する必要がない」とか「科学技術など全く無用だ」という意味ではありません。そうではなくて人生を生きていくための本当の智慧や、「いのちといのちの世界」での感応と申しますか、まん中に入っていくあり方というのは、いわゆる世法上の知識や技術、論理とは別の次元だということです。読み書きや計算や機械の操作や、そういった知識や技術も現実の暮らしの中ではそれなりに必要であり、大切なのです。子どものときからの様々な勉強も学習の努力も、もとより大切であり、決して無用だなどと言っているのではありません。とても大切ではあるけれど、でもそれとは別の次元で、正しい人生を歩むための智慧の体得が必要なのであって、これが無いと知識も技術もほんとうの意味で正しく活かされず、人生の真価も発揮できなくなるというのです。
例えば、同年代の日本人の子どもと、東南アジアの貧しい国の子どもとを較べてみましょう。確かに学科の知識などは日本人の子どもの方が段違いに優れているでしょう。しかし仮に自然の中で生活させてみたらどうでしょう。反対に、東南アジアの子どもたちの方がずっと高い生活能力を発揮するのではないでしょうか。それは自然に対する感受性や生きる力や智慧の違いでしょう。
み仏は、いわば人類に対する「人生の導師」とも申せます。時代も国も超えて、人が幸せに生きるための深い智慧を教えてくださっているわけです。この「いのちある世界」と人間とのあり方、つまり「人と人との魂の感応」、「み仏の魂と人との感応」といった「いのちの世界」は知識だけではどうにもならないのです。
中沢新一氏が河合隼雄氏と対談した『ブッダの夢』(朝日新聞社)という本の中で次のようなことを記しています。中沢氏がチベットで仏教を研究していたころのことです。
当時欧米の学者も仏教に関心を寄せ、新進気鋭の学者が何人も研究に来ていたのですが、その人達に対してチベットの僧がこういうのだそうです。
「あの人たちは確かに語学にも秀れ、自分たちよりずっと分析能力がある。だけど肝心のところがわかっていないなあ」(取意)
また夏目漱石の小説『行人』の主人公である大学教授「一郎」が思想や哲学を専攻していながら、最も身近な妻の心がついに信じられなくて悩み、「自分はいわば地図の上で地理を調査するばかりの者で、現実に自分の足で山河を跋渉(ばっしょう)する実地の人にはついに及ばない。自分は頭の中で物事の周囲を回ってばかりいる迂闊(うかつ)者だ」(取意)と表白するのも同じです。
本物の智慧はいわゆる知識とは別次元だというのはそういうことです。
○「土手の人」にならぬよう
中西悟堂(ごどう)氏(故人)が『アニマ』という雑誌に「土手の人」という題で記していた随筆が、ある本に紹介されていました。その内容をかいつまんで紹介します。
新潟県に瓢湖(ひょうこ)という小さな湖があります。この湖で、従来、学問的には不可能だとされていた野生の白鳥の成鳥の餌づけに成功したのが吉川重三郎(故人)という老人です。
この老人は、ある冬の日、飛来した野生の白鳥の姿を見てすっかり虜(とりこ)になってしまい、以来毎年とりつかれたように餌づけを試み、ついに成功したのです。
老人はただ白鳥が大好きなだけで何の知識もありませんでしたから、餌に何がいいかすら分かりません。それでも、いろいろ工夫をこらし、ついに種モミに茶ガラを混ぜた餌を好むことをつきとめて、あとはひたすら湖に通い続けました。自分の姿も、いつも同じ野良着にし、人に笑われたり、ついには狂人扱いされたりするのも一切意に介せず、来る年も来る年も、まるで馬鹿のように繰り返したのです。そしてついに学会の定説をくつがえして見事に餌づけをしてしまったのでした。
こうなると瓢湖は一躍有名になり、観光の名所にもなって県でも力を入れ始めました。あるとき、大きな調査の会がありました。当日は環境庁(当時)の専門の役人や野鳥の会の会員、生物学等の専門の先生などが多数集まりました。その前で吉川老人が土手を下りて白鳥に例の餌をやる。「コーイコイコイ」と声をかけると湖のあちこちに散っていた白鳥がスーと一斉に集まってくる。けんかをしても、老人が叱るとピタッとやめる。とにかく白鳥と老人との間には絶妙の呼吸があるのです、そこで今度は、土手の上で見ていた専門の人たちが老人のまねをして声をかけ餌をまいてみました。ところが老人以外の者がやると、今度は一斉にくるりと向きをかえて白鳥が逃げていってしまうのです。
老人は文字通り無学なお百姓で、学界の常識はもとより、何の専門知識もありません。これに対して“土手の上の人たち”は専門家で鳥や自然の知識も一般の人よりずっとあるのです。例えば白鳥の渡りのコースとか、繁殖地とか種類などみな知っている。ところが現実に生きた野生の白鳥と心を通わせられるのは、この無智な老人だけ。これはもう、白鳥に対する心のありようの違いとしか申せません。いのちといのちとの交流・感応には単なる知識や理屈は通ぜず、ただ信じ貫く心と実践しかないという実例です。「凡智をとどめ、無智となってこそ仏智がいただける。それも信を貫くことによってのみ可能だ」との「無智宗」の教えはこういう意味なのです。み仏の偉大な智慧をいただくのに、凡夫の知識や理屈は邪魔にこそなれ全く役に立たない、ただ素直な信心を貫くありようのみが通ずるのです。
何事においても力の及ぶ限り努力し、工夫を重ね、学び続けることは大切です。吉川老人も随分工夫・努力をしています。私共信者が御法門を繰り返し聴聞するのも大切なのです。しかし、もっと根本的に大切なのは、そのもととなる心に仏智をいただこうという姿勢です。正しい信心(妙法の受持信唱)を根として心を働かせ、実践・実地を重んじて暮らしていくことが大事なのです。開導聖人は御指南に仰せです。
「愚者(ぐしゃ)はならぬこともなるやうと願ふ心の有(ある)故に[乃至]一分(いちぶん)の智もあらねども自然(じねん)と其意(そのい)に当る也」
(十巻抄第一 扇全十四巻三八一頁)
「信の境(さかい)に入るは無智に限る也。妙は信より外に難入(なんにゅう)也」
(同 扇全十四巻三八一頁)
「信の境に入る」とは信心の極意を会得(えとく)するということです。それは凡夫の知識・分別を捨てて無智の信心に住する以外にはない。いざとなったら常識も我(が)も捨てて、御題目にすがり切っていくとき、はじめて真の妙法の経力をいただくことができるのだと仰せです。
学者が不可能と断じていた野生の白鳥の成鳥と心の交流ができたのは、無学な吉川老人だけ(今は息子さんが継いでいる)でした。上行所伝の御題目は久遠(くおん)のみ仏の魂ともいのちとも申せます。このみ仏のいのち(妙)と末法の凡夫である私たちとが、「いのちの感応」をさせていただく道も、凡智を捨て妙法を無味(むみ)信唱させていただく以外にはないのです。それができず、常識とか分別とか理屈で臨(のぞ)もうとしていては、ついに「土手の人」で終わるしかないのです。知性の力(知識的理解)では入ることができないのが「妙」の世界なのです。御妙判(日女御前御返事・昭定一三七六頁)に
「此御本尊も只信心の二字にをさまれり。以信得入とは此(これ)也。日蓮が弟子旦那等(乃至)無二に信ずる故によて此御本尊の宝塔の中へ入るべきなり」と仰せです。
生きたいのちの核心にすっと入って感応が得られるか、周辺をめぐるのみの観察者・傍観者に終始するか、これは例えば人間関係をはじめあらゆるものごとにおける決定的な相違点となります。お役中は、「無智宗」の教えの真の意味を正しくいただき、無智の信心の力の素晴らしさ、偉大さをまず自身が感得させていただくとともに、他のご信者にもこのことをよく伝えさせていただきましょう。当宗のご信心の核心の一つなのですから。
「智者学匠といふとも凡夫也。舎利弗に及ばぬこといふ迄もなし。」
(十巻抄第一・扇全十四巻三八〇頁上)

佛立研究所 京都市上京区御前通一条上ル Tel:075-461-5802 Fax:075-461-9826
COPYRIGHT 2008 Butsuryu Research Institute Kyoto Japan ALL RIGHT RESERVED.