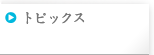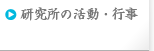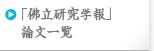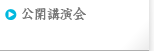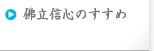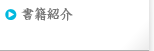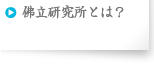-
- 2019
2016
2015
2014
102013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2004
2003
1990
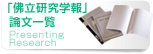
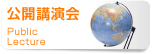
- 仏教のススメの過去の記事
- 2016年 3月
- 2016年 1月
- 2015年 12月
- 2015年 11月
- 2015年 10月
- 2015年 8月
- 2015年 7月
- 2015年 6月
- 2015年 5月
- 2015年 3月
- 2015年 2月
- 2014年 12月
- 2014年 11月
- 2014年 10月
- 2014年 8月
- 2014年 7月
- 2014年 5月
- 2014年 4月
- 2014年 3月
- 2014年 2月
- 2014年 1月
- 2013年 12月
- 2013年 9月
- 2013年 8月
- 2013年 7月
- 2013年 6月
- 2013年 5月
- 2013年 2月
- 2012年 12月
- 2012年 11月
- 2012年 8月
- 2012年 4月
- 2012年 3月
- 2012年 2月
- 2012年 1月
- 2011年 10月
- ㉓妙法こそ大良薬(だいろうやく)
- 2014年10月21日(火)
―色香美味(しっこうみみ)と五感(ごかん)の共働(きょうどう)―
○ 良医病子の(ろういびょうし)譬(たとえ)〈法華経如来寿量品第十六〉
前回では、凡夫の欲が貪欲(とんよく)に趣(おもむ)くことによって自他を共に苦しめることのないように制御・抑制する智慧としての「少欲知足(しょうよくちそく)」の教えの大切さを中心に記し、その一方で、自他の真の幸せを求める向上心(真実の大法を求め、自他の成仏を期する大乗の菩薩の心)を持たず、努力もせず、ただ小法に甘んじてそれでよしとする二乗(声聞〈しょうもん〉と縁覚〈えんがく〉)のあり方は「少欲懈怠(しょうよくけだい)」であり、それは卑屈と慢心とが同居し、その間を揺(ゆ)れ動く心として誡(いまし)めねばならないことも申しあげました。
お役中は、願わくはそのご奉公においてもこの少欲知足の教えを大切にさせていただくと同時に、少欲懈怠とならぬよう注意していただきたいと存じます。
さて今回は、法華経如来寿量品第十六に説かれる有名な譬喩(ひゆ)「良医病子(ろういびょうし)の譬(たとえ)」を紹介しつつ、中でも特に「此大良薬(しだいろうやく) 色香美味(しっこうみみ)」 皆悉具足(かいしつぐそく) 汝等可服(にょとうかぶく)」(此[こ]の大良薬は色香美味、皆悉〈みなことごと〉く具足せり。汝等服すべし)の御文の意について学ばせていただきたいと存じます。先に申しておきますと、「此大良薬」とは他でもない私どもがいただく上行所伝の御題目のことであり、「皆悉具足」とは万法具足のこと、「汝等可服」は信唱せよということなのですが、「色香美味」とあって、色も香も味わいも優れているという御文については、どのように感得させていただくべきなのか、この点について少し詳しく触れたいと存じます。
いずれにせよまず「良医病子の譬」(開結424~426頁)の概略を紹介しておきます(この譬喩は、いわゆる「法華七喩〈ほっけしちゆ〉」の一つで「良医の譬」「良医治子(じし)の譬」等とも称されます)。
ある所に最高の名医がいた。多くの子息がいたが、父の他出中に愚かにも誤って毒薬を服し、毒に中(あた)って悶(もだ)え苦しんでいる所に父が帰宅した。驚いた父は最高の処方によって毒消しの妙薬を調合し、子に与えて言った。「この大良薬は色・香・美味皆(みな)悉く具足せり。汝等服(なんだちふく)すべし。速(すみ)やかに苦悩を除(のぞ)いて復衆(またもろもろ)の患(うれえ)なけん」。
すると多くの子の中でも軽症で判断力を失っていない者(不失心者)は素直に薬を飲み、すぐに回復することができた。ところが重症(毒気深入〈どっけじんにゅう〉)で正気を失い錯乱状態になってしまっていた者(失心者)は、判断力もおかしくなっていたため(心皆顛倒〈しんかいてんどう〉)、良薬を苦(にが)いと言って服さず、更に苦悩を増す有様だった。
そこで名医は薬を飲ませるための一計(方便=巧みなてだて)を案じ、次のように言った。「私は老い衰え死も間近であるが、今からまた他国に行かねばならない。そこで是(こ)の好(よ)き良薬を今留(いまとど)めて此(ここ〉に在(お)く(是好良薬〈ぜこうろうやく〉 今留在此〈こんるざいし〉)。必ず服しなさい。きっとよくなるから」こう言い置いてから他出し、出先から使をやって「お父さんは死んだ」と伝えさせたのだ。
父の死の報に接するや、錯乱していた息子たちも流石(さすが)に驚き悲しみ、「常(つね)に悲感(ひかん)を懐(いだ)いて心遂(こころつい)に醒悟(しょうご)し」(常懐悲感〈じょうえひかん〉 心遂醒悟〈しんすいしょうご〉……深い悲しみに沈むなかでやっと目が醒〈さ〉め、素直な本来の心を取り戻す意)父の薬が大良薬であることも分かって、素直に服したところ、さしもの病悩も皆癒(い)えた。そのことを聞き確かめた名医は再び帰宅し皆に見(みま)えた。
概略以上のような譬え話ですが、この譬喩(長行〈じょうごう〉)の意を重説(じゅうせつ)する偈頌(げじゅ)が「自我得仏来(じがとくぶつらい)」から始まる「自我偈(じがげ)」です。この話の中の名医は久遠(くおん)のみ仏であり、毒を服んで苦悩する多くの子息が衆生です。中でも特に重症患者(毒気深入の失心者)が釈尊滅後末法の私共(三毒強盛〈さんどくごうじょう〉・定業堕獄〈じょうごうだごく〉・未下種〈みげしゅ〉の凡夫〈ぼんぶ〉)であり、今留在此(こんるざいし)の是好良薬(ぜこうろうやく)こそ滅後末法の衆生の為の妙法なのです。名医が方便で他国へ行き死んだと伝えるのは歴史上の釈尊(始成正覚〈しじょうしょうがく〉の仏)の入滅を意味し、実には入滅せず再び見(みま)えるのは、久遠のみ仏の寿命は実は永遠であり、従って釈尊としての入滅は方便のための涅槃[ねはん](非滅現滅〈ひめつげんめつ〉…滅に非〈あら〉ずして滅を現わす)であることを示すとされています。
「常懐悲感(じょうえひかん) 心遂醒悟(しんすいしょうご)」は、わけもなく親に逆らっていた子が、思いがけず、親の死に直面し、その悲哀の中でやっと素直な心を取り戻し、信心を起す姿を彷彿(ほうふつ)とさせるようで、そう思って拝見すると説得力があります。いつもそばにいて、疎(うと)ましくさえ感じていた相手も、もう会えないとなると急に寂しく懐(なつ)かしく思われるというのは、誰しも思い当たるところがあるのではないでしょうか。親のお葬式を通じて、意外に法燈相続やお教化ができることが多い理由の一つはここにあるとも申せます。
○ 「色香美味皆悉具足(しっこうみみかいしつぐそく)」と「五感(ごかん)の共働」
さて問題は「色香美味皆悉具足」の大良薬である御題目であるのに、私共末法の凡夫は、毒気深入[どっけじんにゅう](三毒強盛)で心が皆顛倒(てんどう)しており、正しい判断能力がなく、すべてさかさまな見方しかできなくて、苦(にが)くて臭いなどと感じ、素直に有難く服する(信じ唱える)ことが中々にできにくいということです。
この点につき開導聖人は次のように仰せです。
○ 題・妙法五字万法具足(まんぼうぐそく)
御教歌
いろもかもめに見えずしてそなはれる ことは利生に顕れにけり
(開化要談・体・扇全13巻340頁)
御教歌お書添え御指南
「御供水(おこうずい) 白き水に見えれ共(ども) 色香美味(しっこうみみ)。妙法五字 黒き文字と見え 万法具足はみえず。
何にても所願具足(しょがんぐそく)するをもて いろか顕(あらわ)るゝは事相(じそう)也」
○ 題・絶待妙(ぜったいみょう)
御教歌
世の人を救ふ御法(みのり)のはす[(はちす)]の花 これにくらぶる色も香(か)もなし
(仏法大要・上・扇全11巻43頁)
末法の衆生を救うことができる南無妙法蓮華経の御題目・妙法五字にはみ仏のすべての功徳が具(そな)わっており、色も香りもすぐれ、他に較(くら)べるべくもない最高の御法であることは、凡夫には感知し難いけれども、現証(ご利生)によってそれと腑(ふ)におちる。これを感得すべく、まず素直に妙法を受持信唱させていただくことが大切だとの意です。
御供水は、凡夫の目にはただの無色透明の水にしか見えないが、実は妙法の功徳水であり、色香美味である。御題目は黒い文字としか見えず、その五字七字の中に万法が具足していることは感見し難いが、ご利生という事実・形に対したとき、凡夫にもそれと感得できるのだと仰せです。「絶待妙(ぜったいみょう)」というのは相待妙(そうたいみょう)に対する語で、元来が絶対のもので他と比較相対できない、そういうことをもともと超越しているという意です。
ただ、それにしても、では「色香美味」等はいわば単に譬えなのか、というと決してそうではありません。実はこれは言葉を超えたものであると同時に現実にその通りに感得し得るものなのです。そのことの理解の一助となるのではないかと思う一文を紹介しておきたいと存じます。
○ 「この犬“おいちい”ネ」
これは『老いの発見3……老いの思想』(岩波書店・1987年)の中で鶴見俊輔氏が紹介している戸井田道三氏(能と伝統芸能の研究者)の、自身の「おいしい犬―幽玄(ゆうげん)」のメモに拠る文章の一節です。少々長くなりますが次の通りです(同書35頁・一部割愛)。
「昔、私の家に小さな犬を飼っていたことがある。友人が三つくらいの男の子をつれて遊びに来た。その子が小さな犬をダッコしてひどくかわいがった。『この犬おいちいネ』と彼は言った。かわいいという言葉をまだ知らなかったのかもしれない。その場の雰囲気や情況からいって『おいしい』というのはまことに適切であった。まわりにいたおとなどもは皆笑ったが、これ以上にうまい表現は不可能とさえ思えた。
笑ったのは『かわいい』というべき情緒を味覚でいった錯誤(さくご)に対してであった。しかしおとなだってつねにそのような間違ったいいかたはしている。たとえば『苦(にが)みばしったいい男』とか『少し甘い女』などいくらでもある。但しこれは常用されているあいだに味覚の応用とは認められなくなった。やはり適切な言葉として容認されたのであろう。つまり視・味・嗅・聴・触などの感覚器官とそれに対応する言葉とをつなぐ回線がまちがった方が適切だという場合もありうるわけである。それが可能なのはいわゆる五感がひとりの身体に統一されているからで、五感の各々が別に感じられると同時に、いっしょに働いているからにちがいない。(中略)『この犬おいちい』などというのは、たしかにまちがいである。しかし、まちがえることによって分類以前の混沌(こんとん)にさかのぼることにはならないであろうか。混沌をつかまえるためには言語の明晰(めいせき)以前にさかのぼる必要があり、それがあるから身体の自発性が共感覚を刺激する作用をするのではないだろうか」(戸井田道三『忘れの構造』筑摩書房・1984年)
幼児が「この犬おいちいネ」と言ったその言葉は、子犬の暖かさや匂い、柔らかな感触、たべてしまいたいような可愛さ等々、そのすべてを身(からだ)と心の全部でそのまま丸ごと受けとめ、感極まって発せられたものであり、文字通り五識六識が一体となった表現です。そういえば「痛い思い」「甘い言葉」「冷たい仕打ち」「暖かい色」などの表現は実際、無数にあり、すでに日常生活で何の違和感もなく自然に使っています。
仏教では六種の感官能力を眼(げん)・耳(に)・鼻(び)・舌(ぜつ)・身(しん)・意(に)の六根(ろっこん)とし、これによって六識(ろくいき)が生じ、色(しき)・声(しょう)・香(こう)・味(み)・触(そく)・法(ほう)の六境(ろっきょう)を認識するとされますが、さらに「六根互用(ろっこんごゆう)」といって、各根が互いに他の五根の作用・能力を具することも説かれます。例えば鼻で聞いたり、味わったりもできるわけで「聞香(もんこう)」という言葉もあります。通常の感覚器官は五根(眼・耳・鼻・舌・身)で、これが色・声・香・味・触を感じ認識・識別しているのですが、音や香りや味に色を感じることも決して不思議なことではなく、実は五感が共働し、一体となって、言葉によって分類される以前の本然(ほんねん)のものを体全体で感得することも、私たちにはできるのです。
確かに通常、御題目は眼には黒い文字にしか見えず、御供水は無色透明の水としてしか認識できませんが、ご利生をいただき、歓喜の心で唱え服(ふく)するときは、御題目は輝き、御供水は匂いたつ甘露(かんろ)だと感得させていただくこともできるのです。
「此大良薬 色香美味 皆悉具足」の御文を真の意で感得させていただくには、やはり素直な「柔和質直(にゅうわしちじき)の信心」が要(かなめ)となるのです。

佛立研究所 京都市上京区御前通一条上ル Tel:075-461-5802 Fax:075-461-9826
COPYRIGHT 2008 Butsuryu Research Institute Kyoto Japan ALL RIGHT RESERVED.